

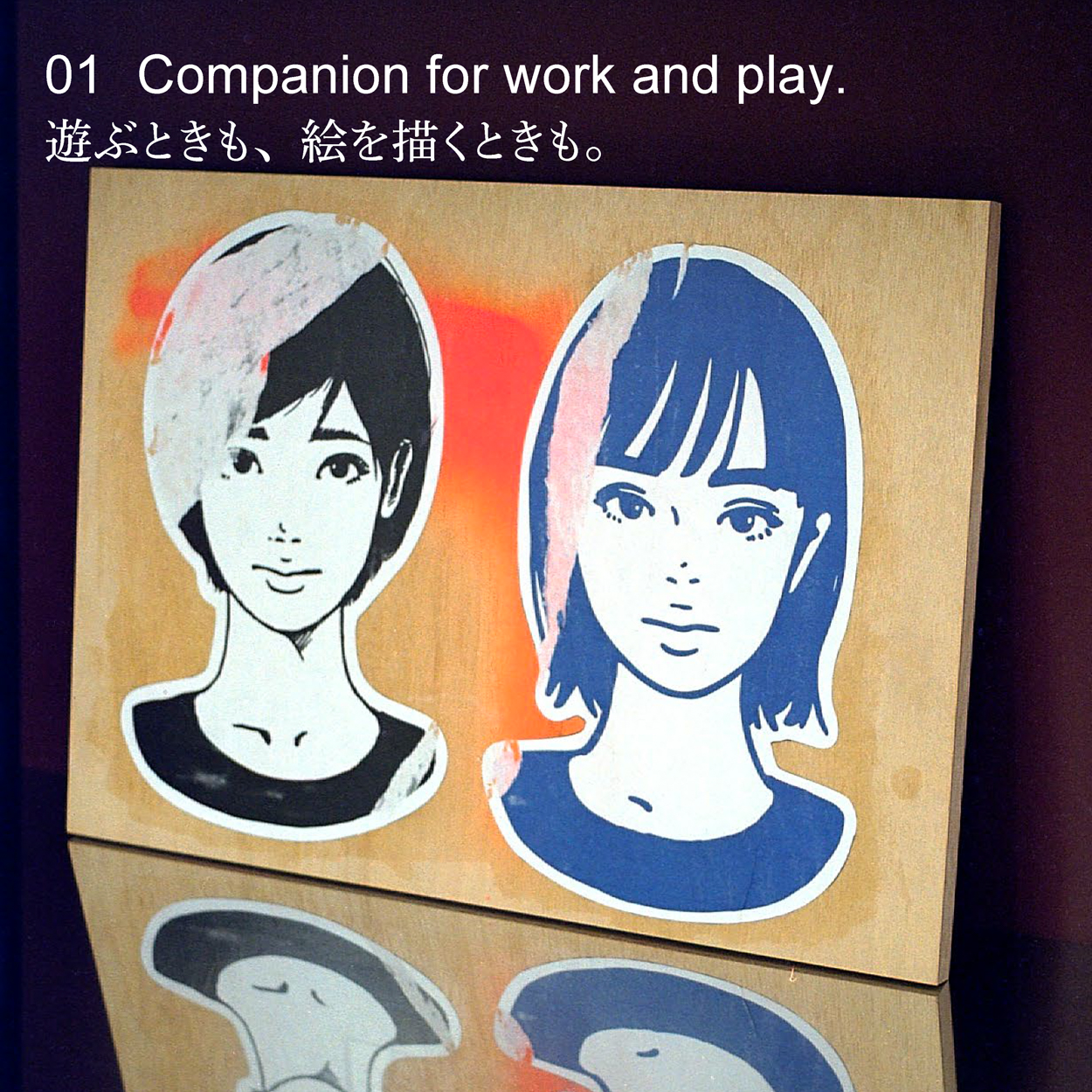
1988年生まれ。2006年頃から福岡で活動を開始。2010年頃にシンプルな背景に女性を描く作風が確立。2020年には福岡市美術館に壁画作品『Untitled』を描き話題に。2024年には福岡市美術館で初の大規模個展『ADAPTION – KYNE』を開催。
ー かねてよりGramicciを愛用していただいているとのことですが、普段はどれを穿くことが多いですか?
KYNE:多分、一番定番のやつだと思います。今日も穿いてるやつなんですけど。

ー ありがとうございます。『GRAMICCI PANT』というモデルです。良い感じにアジが出ていますね。
KYNE:だいぶ出てきましたね。制作のときも、遊びに行くときも穿いているので。気に入った洋服があったら何着も同じものを買ってそればっかりを着回すタイプで、これも同じやつを何本か持っています。
ー 制作の際にも穿いていただいているんですね。絵の具が跳ねたりしていないので、てっきり普段着なのかと。
KYNE:あまり飛ばさないタイプなんですよね。
ー『GRAMICCI PANT』はどういったところがご自身にフィットしていると感じますか?
KYNE:このベルトがすごく便利なのと、程よく太めのシルエットも好みです。あとは、タフだけどハイテク過ぎないところ。こういうパンツだと、ナイロンとかの化学繊維が入っていてシャカシャカした素材のものが多いと思うんですけど、なんとなく熱に弱そうな感じがして。バイクが好きで普段からよく乗っているので、そういう素材のものだと少し不安というか。
GRAMICCI PANT
1980年代に誕生したGramicciを代表する1本。180度の開脚を可能としたガセットクロッチ、片手で調整できるウェビングベルト&イージーウェスト。クライマーたちの要求に応えるべく搭載した革新的な機能は、アウトドア愛好家のみならず、自然と街をシームレスに移動する都市生活者のライフスタイルにもフィットする。
ー 確かに、溶けそうですね。ちなみにバイクは何に乗ってらっしゃるんですか?
KYNE:2台乗ってて、HONDAの『CB400FOUR』と、カワサキの『Z1000LTD』です。

ー けっこうヤンチャなバイクだと思うんですけど、ご自身の趣味嗜好は、そこまで作品に表出しないタイプなんですね。
KYNE:そうですね。わざわざ出すことはしないタイプです。それはそれ、これはこれ、というか。
ー 今はどういうものがインスピレーション源になっているんですか?
KYNE:そういうものもあまりないんですけど、最近は、小中学生の頃に好きだった映像や本を改めて見返したりしています。そこからなんとなく影響を受けたりってのはあるかもしれないですね。当時の雑誌とかを中古で探して買ってみて、「ああ、こんな感じだったな〜」みたいな。
ー それは本棚にもたくさん並んでいる『STUDIO VOICE』だったり。
KYNE:はい。あとは『relax』とか。
ー やっぱり雑誌から得たものは多いですか。
KYNE:情報源はほぼ雑誌でしたね。グラフィティだったり、ストリートアートの情報は当時その手の雑誌でしか得ることができなかったので。ファッション誌なんかに載ってるストリートアーティストやグラフィティライターの人たちのインタビューを見て「こんな感じで描いてるんだ」とか「こんな服装してるんだ」とか。いろいろと影響を受けていましたね。

ー グラフィティはKYNEさんを構成するキーワードのひとつかと思いますが、どのように興味を持ち始めたんですか?
KYNE:10代になると周りの友だちとスケートボードをやるようになって、県内の滑れるスポットに行くとだいたいグラフィティがあったんです。そのときはそれを“グラフィティ”と認識していたわけではなく、でも近くに描かれている暴走族の落書きとはちょっと違う感じがするな、くらいの認識でした。たまに増えていたりもして「これはなんだろう?」「誰が描いているんだろう?」みたいな。
ー 暴走族のは「●すぞ」とかですよね。
KYNE:そうですそうです。あとはチームの名前? “●●連合”みたいなのとか。そういうのとは違って、キャラクターとかイラストっぽいものもあったり、筆記体のサインっぽいものもあったり、なんとなく、ちょっとアートっぽい感じがするなと。もともと絵を描いたり、見たりするのは好きな方だったので、スケボーがてらグラフィティを見に行く、みたいな時期がしばらく続いていました。自分も10代後半の頃から街に描いたり、ステッカーでタギングするようになったんですけど、そうしているうちに、グラフィティライターの知り合いができたりもしました。そうしてしばらく街での活動を続けていたんですけど、もうやることはないですね。

ー 街での活動が恋しくなるときはないんですか?
KYNE:まったくないです。捕まっちゃいますし、なにより、もう自分の絵を多くの人が知ってしまっているので。みんなに“謎”を残すのが楽しかったんですよね。僕自身も、街に描かれたグラフィティが“謎”だったから面白いと感じていたところがあって。
ー “謎”ですか。
KYNE:「これは誰が描いたんだろう?」って疑問もそうなんですけど、「これはアーティストの名前なのかな?」とか「このモチーフはあそこでも見たことあるから同じ人が描いているんだろうな」とか、昨日まで何もなかったところに突然現れている感じとか。最初は何もかもが分からなくて、いろいろと想像するのが楽しかったんですよね。でも、街で遊んでいるうちに、誰が描いたかを知る機会があったり、描いている人と知り合ったりしているうちに、自分を興奮させていた“謎”がだんだんと無くなっていくのを感じてしまって。
ー 分かる気はします。
KYNE:当時は楽しかったですけどね。“街を使った遊び”って感じで。今はもう自分が描きたいとは思わないです。

天神の街に現存するKYNEのステッカー。
ー 今のKYNEさんのスタイルからもグラフィティの影響は感じ取れますが、ご自身としては、どういった部分にグラフィティのエッセンスが残っていると感じますか?
KYNE:技法よりは精神性の部分で、グラフィティって言うまでもなく、視覚的な効果が最重要なんです。僕はポスターやステッカーでやることが多かったんですけど、限られた面積で遠くまで目を引くように描く感覚は、今も残ってるように思います。やっぱり細かく繊細に描かれたものって、街にあっても目を引かなくて。シンプルで、強さがあるものじゃないと、パッと入ってこないんです。だんだんと活動の場が街からそうじゃないところに変わっていったので、それに応じて手法も変化していきましたけどね。

ー やはり発表の場が変わると、アウトプットの姿勢も変わる?
KYNE:変わるというよりは、意識的に変えていってますね。モチーフの選び方や構図の作り方は特に。やっぱり街では細かく描き込まずにグッとモチーフに寄ってインパクトを出す、みたいな描き方がメインでしたけど、美術館で展示をするようになってからは、だんだんと絵画的にも成立する構図やモチーフ選びを意識するようになりました。とはいえ、これまで描いていたものをベースにしながら、あえて絵画っぽい構図を作ったり、人物だけでなく静物画も描いてみたり、古典的な美術を自分の方法論に落とし込んだらこんな感じ、というところは意識しています。

ー 「KYNEガール」はある種フォーマット的に作られていますが、少しずつ変化していってるんですね。
KYNE:「これはこういうものだ」と脳に刷り込まれたものを、少し変化させたときの視覚的な面白さみたいなのがすごく好きなんですよね。常にどんどん新しいものを作るよりは1つのものを変化させたり、シリーズ展開させていきたいなと思っていて。
ー 並べて見ると変化は分かりますが、どれが最新でどれが古いものなのかは、正直分からないかもしれないです。
KYNE:なるべく短いスパンでの“流行”みたいなものは取り入れず、普遍的なものを描こうと意識はしています。ただ、長い目で見て、何十年後かに感じる時代性みたいなものはあってもいいのかなって思っています。言い方が難しいですが、僕たちは昔のものを振り返るときに、それを「昔のものである」という前提のもとで「懐かしくて良いよね」と見ているけれど、いつの時代でも「今良いよね」ってなるものが作れたら良いですよね。
ー 「KYNEガール」たちは髪型も洋服もそれぞれですが、そのあたりの「時代性」はどのように考えていますか?
KYNE:なるべく情報としてのノイズを減らしたいので、そういった記号的なものにも“意味”や“流行”は含んでいないです。絵画の構成上、2色、3色で映えるバランスにしようとか、そういうことは考えていますけどね。

ー ちなみに、大学では日本画専攻だったんだとか。
KYNE:はい。高校でデザイン科に入学するんですけど、美術をやるぞ、デザインをやるぞ、みたいな強い意志のもとで進学したわけではなくて。絵を描くのは好きだったけど勉強は得意ではなかったので、ほとんど消去法みたいな感じでした。大学もその高校の附属大にそのまま進学して、そこで日本画の専攻を選んだんですけど、それもせっかくだったらやったことのない技術を学べて、使ったことない画材を使える日本画かな、みたいな、軽いノリでした。
ー 日本画の技術が今のご自身の作品に反映されていることは公言されていますが、どういった部分ですか? 「日本画」というものがパッとイメージできなくて。
KYNE:日本画は油彩や水彩とは画材が違って、濡れているときと乾いているときとでけっこう色が変わるので、コントロールが難しいんです。なので、下絵を作ったりして計画的に描かないといけないし、油絵みたいにアドリブ性が入り込む感じでもなくて。そういう“作り方”の部分は、今の制作方法にも通ずる部分かなと思います。

ー ちなみに、6月末に大規模な個展を終えて、近頃はどのようにお過ごしですか?
KYNE:ちょっと制作もしつつ、わりとゆったり過ごしています。友だちに会いに東京に行ったり、外で遊んだり、YouTubeを見たり。
ー YouTubeはどんなものを見ているんですか?
KYNE:スクランブル交差点とか歌舞伎町とか、都会の街を定点で映しているライブ配信が好きで、そういうのを見たり、個人の配信者が歩きながら街を撮影しているライブ配信を見たり……まったく作品に反映されることはないんですけど(笑)、なぜかずっと見ちゃってますね。ライブ配信の文化ってかなりヤバいと思っていて、これからどうなっていくのか、個人的に気になっています。偶然にいろんな人や事象が映り込んで、自分も映り込もうと思ったら映り込むこともできて、配信が終わってアーカイブされなければ全部なかったことになる。すごいですよね。一昔前だったらありえなかったことですし。
ー 言われてみれば確かに。街での活動はもうしないとおっしゃっていましたが、興味関心はずっと「街」に向いているんですね。
KYNE:そうですね。街から活動を始めましたし、街から教わったことがたくさんあるので。ずっと街に興味があるんですよね。個人的には、アートって美術館やギャラリーだけで出会えるものではないと思っていて。僕自身、街のいろんなところでアートと出会って、興味をひかれて、それによって街の見方、モノの見方、楽しみ方が変わりました。そういう体験があったからこそ、今があるように思うんですよね。


