

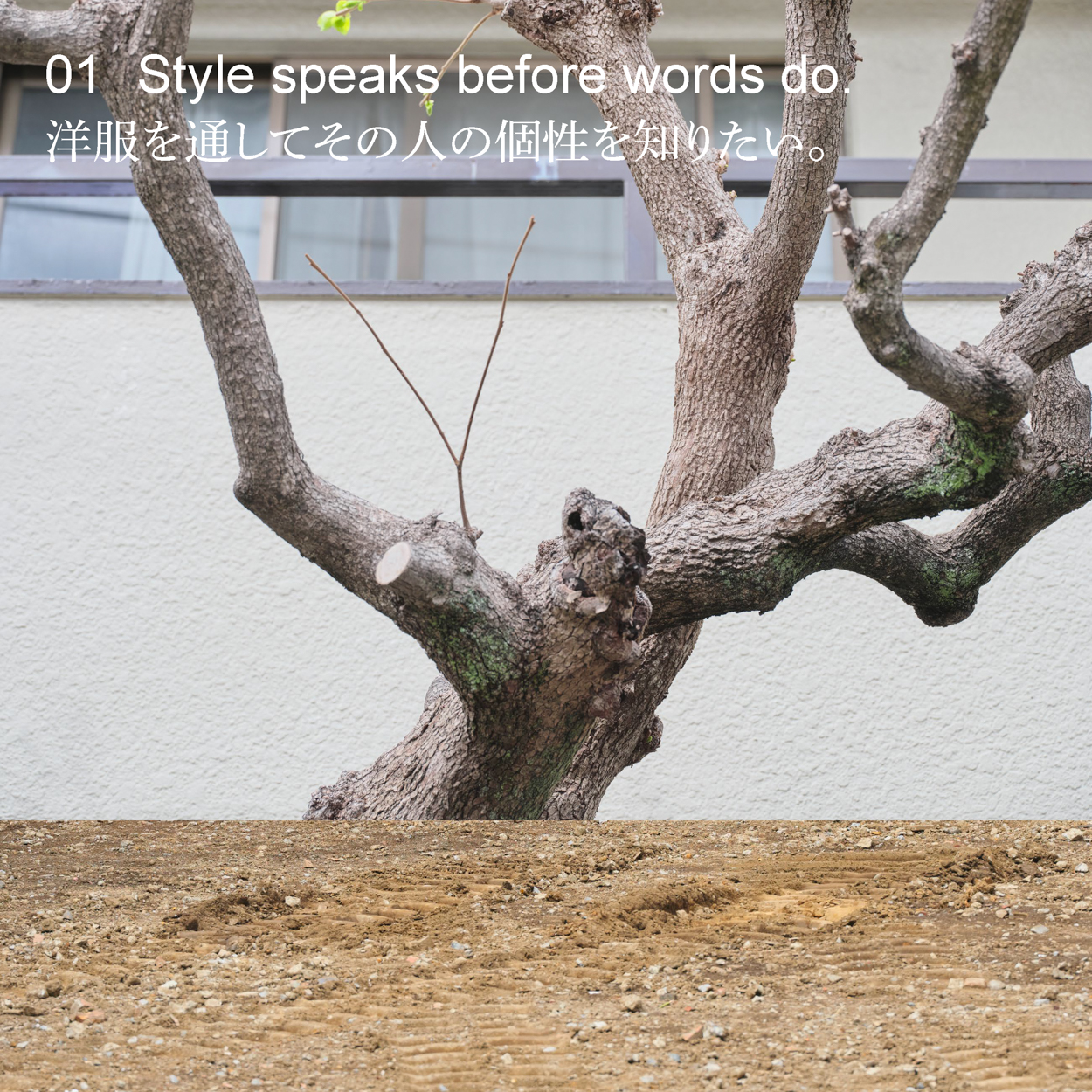
梶雄太 / スタイリスト
1974年、東京都生まれ。アシスタントを経て、1998年からスタイリストとしてのキャリアをスタート。雑誌、広告、映画など幅広く活動する傍ら、映像制作や執筆などジャンルを問わず表現をし続ける。Instagram @yutakaji_
ー 90年代の『HOTDOG PRESS』で梶さんがGramicciをご紹介いただいているのを見て、今回オファーさせていただきました。
梶:うっすらですが、記憶にあります。デカいTシャツの袖だけを切ったようなノースリーブのトップスがあって、それが好きで『プロペラ』で何着も買っていました。一時期そればっかり着ていましたね。10代の頃とかだと思うんですけど。
ー 日頃からたくさんの洋服に触れている梶さんにとって、Gramicciってどんな印象がありますか?
梶:ほとんどのセレクトショップが別注していて、誰でもラクに着られて、誰が着てもちょうどいい感じになるブランド。そんなイメージがありました。昔はオシャレが好きでこだわりも強かったけど、今はもう落ち着いてパパやってます、って人が休日に穿いているような……でも、ひさしぶりに穿いてみて、ビックリしました。すごく良かったから。「あれ? 良くね? こんなだったっけ?」みたいな。

ー 今日穿いていただいたのが『CANVAS EQT PANT』という、この春夏の新作です。
梶:Gramicciはそれこそ90年代に『プロペラ』や『バックドロップ』で太いパンツを買って、ラクで良く穿いていましたが、今はこうなっているんですね。そのときに穿いていたやつはちょっとテーパードしていた記憶がありますが、それと比べてもこれはシルエットが都会的で、すごくモダンじゃないですか。ロンドンのストリートの子たちが穿いていそうな感じというか。西海岸由来のアウトドアブランドだとばかり思っていたけれど、ヨーロッパの洗練された雰囲気を感じます。実際に手に取ってみたら、僕みたいに驚く人も多いんじゃないですかね。
CANVAS EQT PANT
コットンとヘンプを混紡した9オンスのキャンバス生地は、タフな質感とガーメントダイによる豊かな色味が特徴。フロントのカーゴポケットを含む大小8つのポケットは、街のみでなく、アクティブなシーンでの活躍も期待できる。
ー 嬉しいフィードバックをありがとうございます。
梶:もともと穿き心地が良いイメージはありましたし、ラクさを求めて買う人も多いんでしょうけど、全然それだけじゃないですね。結構しれっとこういう深いアイテムを出しているので、良い意味で期待を裏切られました。「ラクだし、適当に穿いてもそれなりに良い感じになる」みたいな、そういうアイテムってみんなに求められがちですけど、僕はスタイリストとして、やっぱり“ラクでそれなり”なものには賛同できなくて。言葉を選ばずに言えば好きになれないんです。
ー 個性が出ないというか。
梶:そうそう、みんな同じに見えちゃうんですよ。僕は、洋服を通してその人の個性を知りたいのに。みんなそれぞれに見ているものや考えていることがあって、それが洋服の選び方や着方にも現れて、どうしたって個性が滲み出ちゃうのがファッションだと思っているんですが、“ラクでそれなり”なものが増えて、その人らしさが見えづらくなりましたよね。

ー 確かにそう感じています。それって、どうしてなんでしょうね。
梶:うーん、きっとみんな失敗したくないんですよね。恥もかきたくない。分かりますけど、やっぱり経験って大事。ファッションの恥なんてタカが知れてるし、だれかに「変だな」と思われたとしてもどうせ次の日には忘れてるんだから(笑)。どんどん挑戦したほうが良いと思うんですよ。失敗にこそ旨みがあるし、ファッションって失敗すればするほど上手になっていきますから。
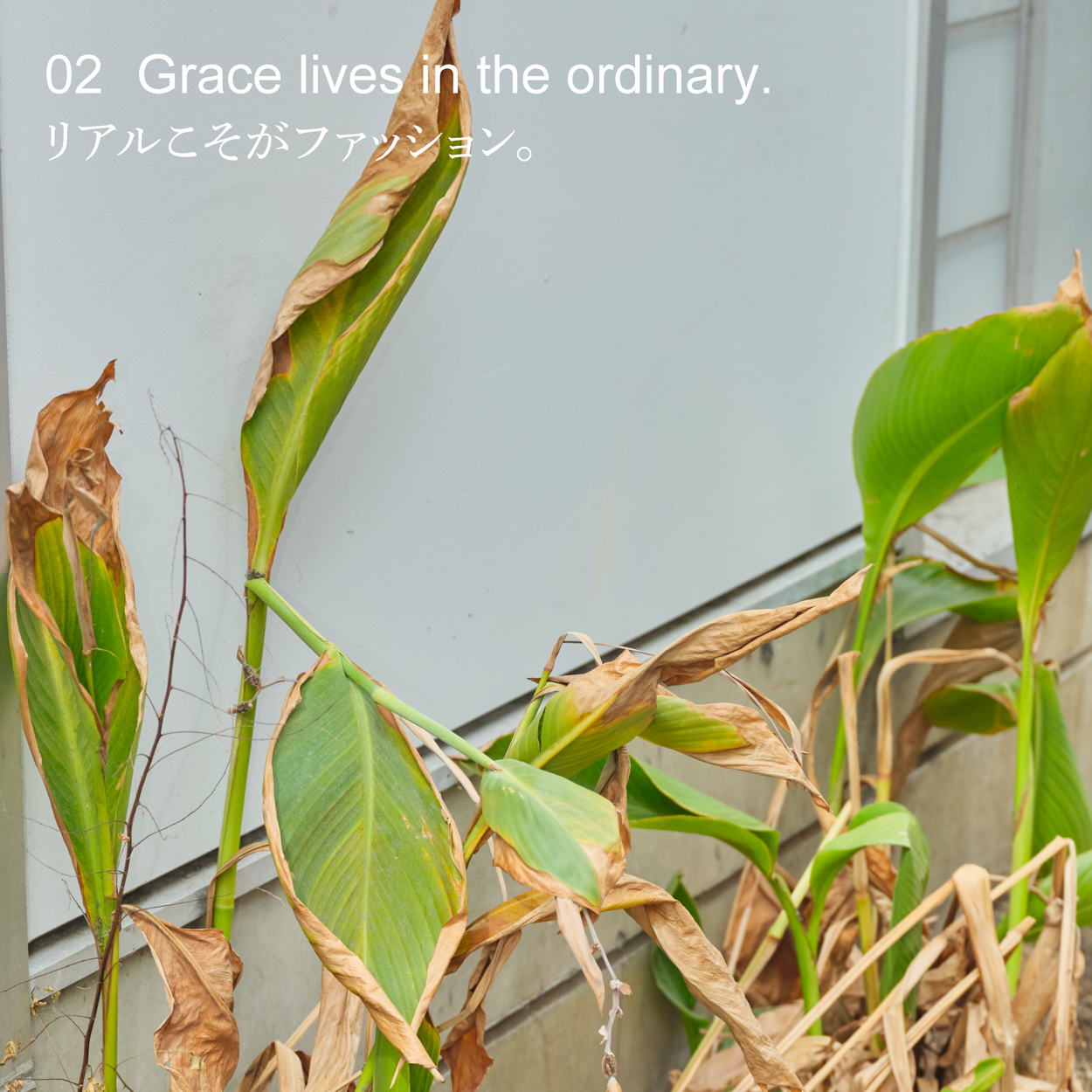
ー いろんなところでお話しされていることかと思いますが、梶さんはなぜスタイリストになったんですか?
梶:両親ともアパレルの仕事をしていて、親戚にはカメラマンや雑誌編集者がいて、ファッションとは身近な家系だったんです。それもあり、小さい頃からずっと洋服は好きでしたが、10代の後半になって将来のことを考え始めたときに、洋服屋さんになるイメージは沸いてこなかった。そんなタイミングに、良く遊んでくれていた先輩たちのひとりにスタイリストをやっている人がいて、たまに手伝いで現場に呼んでくれるようになったんです。そのときに初めて“スタイリスト”という職業があることを知ったんですが(笑)、「へえ、こんな世界があるのか」と。刺激的な環境でしたし、しかもこれでお金もらえるんだ? と思って。そこからアシスタントをやって、独立して、もう30年弱になりますね。

ー その30年弱のなかで、梶さんのスタイルはどのように磨かれていったんですか? スタイリングのみでなく、起用するモデルやロケ地、そういうものを含めてひと目で梶さんのエディトリアルだと分かるので、気になっていまして。
梶:今の考え方につながっているきっかけのようなものをあえて挙げるのなら、『Free&Easy』という雑誌での仕事が特に印象に残っています。知り合いの編集者から「すごく自由な雑誌だから、多分梶と合うと思うよ」と紹介されて、編集部に遊びに行ったらいきなり編集会議に参加させられて(笑)。本当にフリーでイージーな雑誌で、いろいろと自由にやらせてもらいました。結構斜め上っぽいこととかも。
ー たとえば、どのような企画が印象に残っていますか?
梶:「必ずしもカメラマンに撮ってもらう必要ってないかもな」と、林家ペーさんに撮影をお願いして、林屋パー子さん、江頭2:50さん、大木凡人さんにモデルをお願いしたりとか。

ー すごいですね。“ファッション写真”で思い浮かべるものとは全然異なるような。
梶:いわゆる“ファッション写真”って、やっぱりリアルじゃないんですよ。もちろん世にでているファッション写真はあえて非現実的に作っている部分も大いにあるとは思いますが。ただ、僕はリアルこそが“ファッション”だと感じるんです。身の回りの人をモデルにして普段生活しているような場所でロケをするのも、そういう理由です。大きいことを言うようですが、スタイリストの仕事は洋服を選んで着せることではなく、洋服を介して何を伝えられるかだと思うんです。もちろん、洋服自体のかっこよさやかわいさに引っ張ってもらうこともありますが、たとえば、それを着ることの必然性── モデルの心持ちの部分ですよね。そういう目に見えないさまざまな要素が1枚の写真に介入して、交差することによって、スタイリングの見え方って不思議なほどに変わってきますから。
ー それは、このおよそ30年ほどのキャリアのなかで形成されていった考え方なんですか?
梶:社会の変化に応じて自然と変わっていってる部分もありますが、それでも根幹は変えずにここまでやってこれたとは思っています。花が咲くか分からない種をひたすらに撒いて、一生懸命に耕して、広場がちょっとずつ完成して、だんだんと新しい遊びができるようになってきた感じです。だから、懲りずに続けていると良いことあるんだなって。
ー スタイリストの、どういった部分にやりがいや楽しさを感じていますか?
梶:スタイリストを始めた当初から今も変わらず、常に自分にとって新しいことをやりたいと思っていて、ありがたいことにここ近年も新しいことにトライさせてもらっているんですが、その度に、頭が膨れ上がるんですよ。アイデアがどんどん浮かんできちゃって。「やれたら面白そうだけど、本当にできるのかな?」みたいな。自分でも見たことないことをやろうとしているから、企画が動いてすぐは期待と不安が半々なんですよ。でも成功させるためにいろいろと動いているうちにだんだん整ってきて、不安も晴れてきて、ゴールも見えてきて「あとはやるだけだ」みたいな瞬間が訪れるんですよね。その瞬間が一番好きです。もちろん不安を抱えながら進めるプロセスも楽しんでいますけどね。

ー 感性や感覚みたいなことを重んじる人なのかな、と思いつつ、考えることにもすごく時間を使うんですね。
梶:感覚も理性も、どっちも大事ですよね。20代の頃は何も考えないで感覚だけでやってきて、振り返ると、その頃って本当に僕がやっていること、表現したいことが理解してもらえなかったんですよ。気持ちとしては今も同じことをやっているんですけど、伝わり方、届き方が今とは全然ちがう。でもそれって、僕が自分自身をプレゼンする能力がなかったからだと思うんです。僕自身がどういう人間かを伝えられていなかったから、そりゃ理解もしてもらえない。本や映画はずっと好きだったから、そういうものから伝え方を学んだりしたこともありましたが、今は時代も変わったからか、少しずついろんなことがやりやすくなっているし、受け入れてもらえている感じはしています。
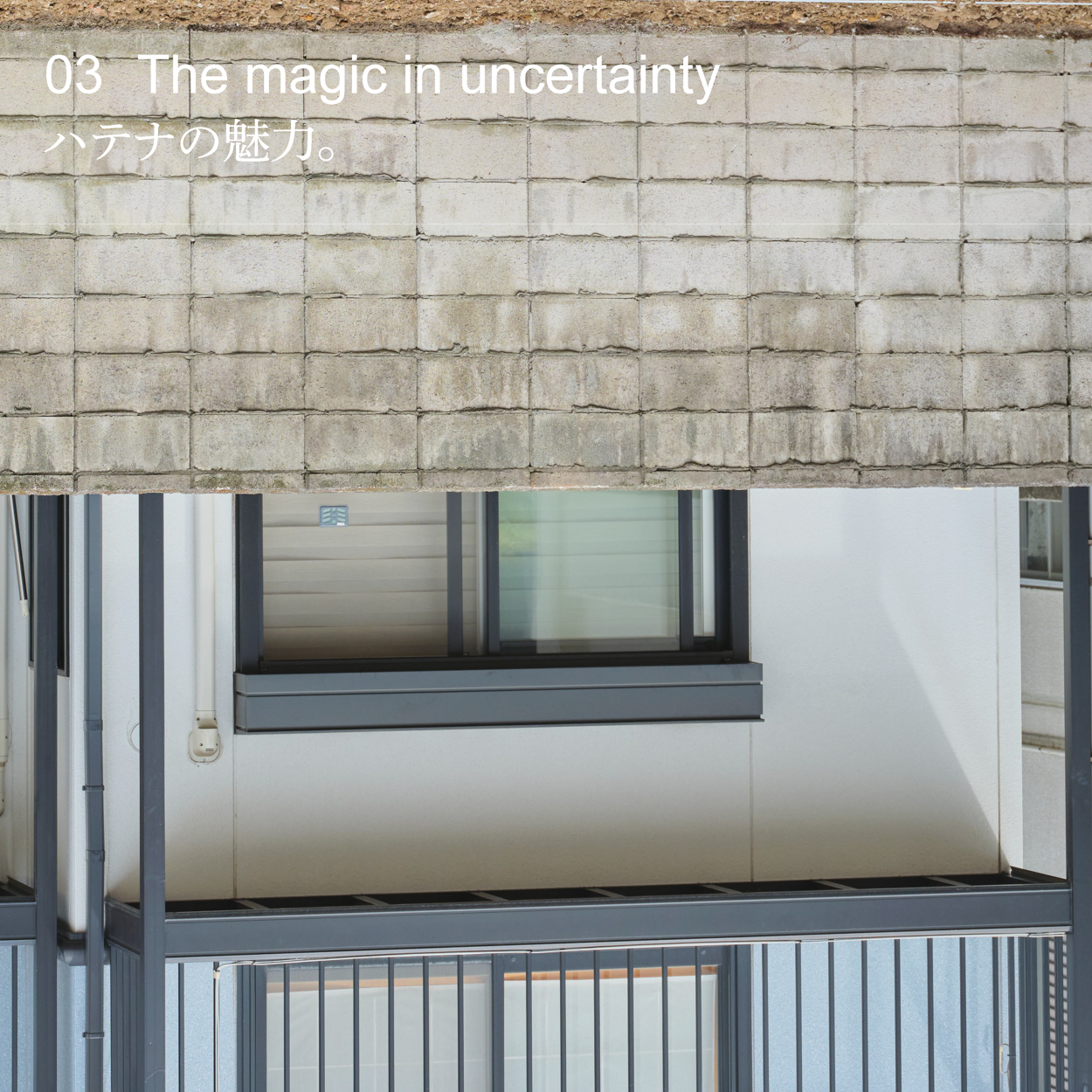
ー 新しいことといえば、近年は本も作ってらっしゃいますよね。
梶:『編集長』というフリーマガジンを年に2冊作らせてもらっています。先日配布開始になったものでもう3冊目ですね。パンツブランドのBARNSTORMERに協賛してもらい、一冊丸ごと“チノパン”にまつわるコンテンツで、取材したり、エッセイ書いたり、ファッションシューティングしたり。
ー 3冊やってみていかがですか?
梶:VOL.1とVOL.2はおおよそ自分の周囲のことだけで作ったんですよ。予算が限られていた都合もありますけど、何よりそれが一番シンプルだと思ったので。どっちもすごく評判が良く、頑張って作ったから嬉しかったんですけど、そのぶん、VOL.3はもっと良いものが求められているなとプレッシャーを感じつつ作りました。頑張って予算を上げてもらって、たくさん人を巻き込んで作ったんですが、すごく難しいことが多くて……入稿したときは心底ホッとしましたね。

ー どういった部分を難しいと感じましたか?
梶:私事じゃないと、全然手が進まなくなっちゃうんですよ。たとえば、人の話を聞いて、それを文章にするのが本当に難しくて。僕の脳はそういうふうに作られていないんだ、と思い知りました(笑)。VOL.3はいろんな人に協力してもらってるから、立場的にも本当に“編集長”って感じで。依頼する側って難しいんだなと。スタイリスト業は逆で、依頼される側だからこそ“自分”を出せるんですよね。そんな感じで、VOL.3はたくさんのことを乗り越えたから、そのぶん思い入れも強いです。僕の馴染みの飲食店や書店、小売店に置いてあるので、見かけたらぜひ手に取ってみてほしいですね。
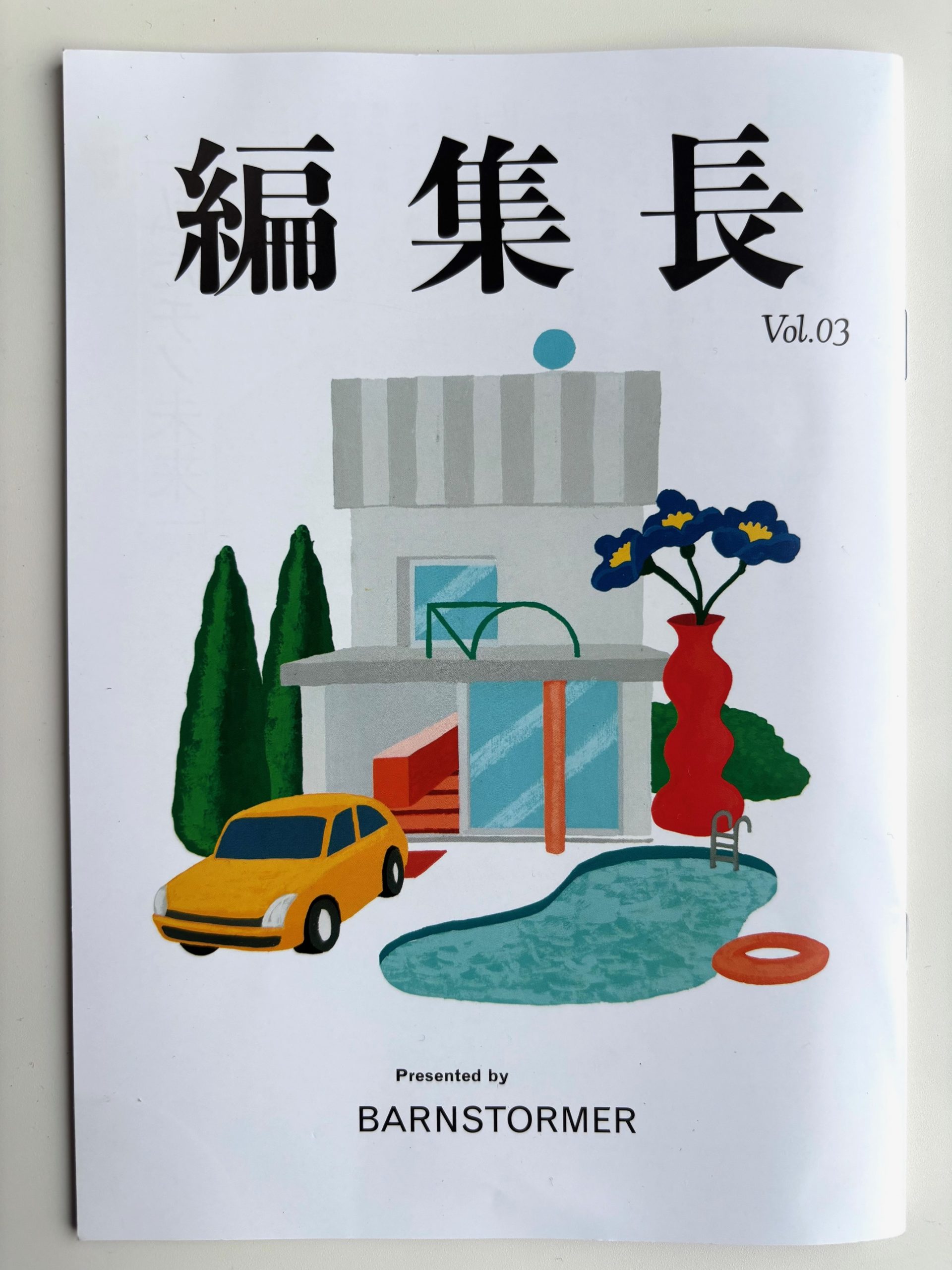
ー 3冊もやっていると、だいぶこなれてきそうですね。
梶:本としてまとめることについては回を重ねるごとに上手になっていってる実感があります。ただ、上手すぎるものって面白くないから、上手くなりすぎないようにはしていますけどね。
ー スタイリングにもそういうところはあるんですか?
梶:全部の表現にあると思いますよ。デザインしすぎない、整えすぎない美学、みたいな。やっぱり“完成する一歩手前”ってすごく色気があるんです。少し危うい雰囲気もあるし、まだ何にもなっていなくて、それゆえに唯一無二というか。完成されたものってもうその時点から記号化されて、“それ”でしかなくなっちゃう。それよりも「なんだかよく分からないな。でもなんか良いね」とハテナが浮かぶようなモノやコトって、個人的にすごく魅力があると感じるんです。

ー なるほど。分かるような気がします。
梶:たまによく分からない服装してるやつとか、意味不明な言動や行動をするやつとかいますけど、本当に最高ですよね。なんの記号にも当てはまらないし、なんのレッテルも貼れないんだもん。僕自身、そういう人間に憧れがあります。簡単には分かってもらえないくらい先に行きたいというか。
ー 「かっこいい」や「面白い」はある意味レッテルを貼られてしまっていると。
梶:そうそう。それよりも「分からない」の方がずっと奥行きがあると思うし、分からないことを分からないまま楽しむのって、すごく豊かなことだと思うんですよね。


