

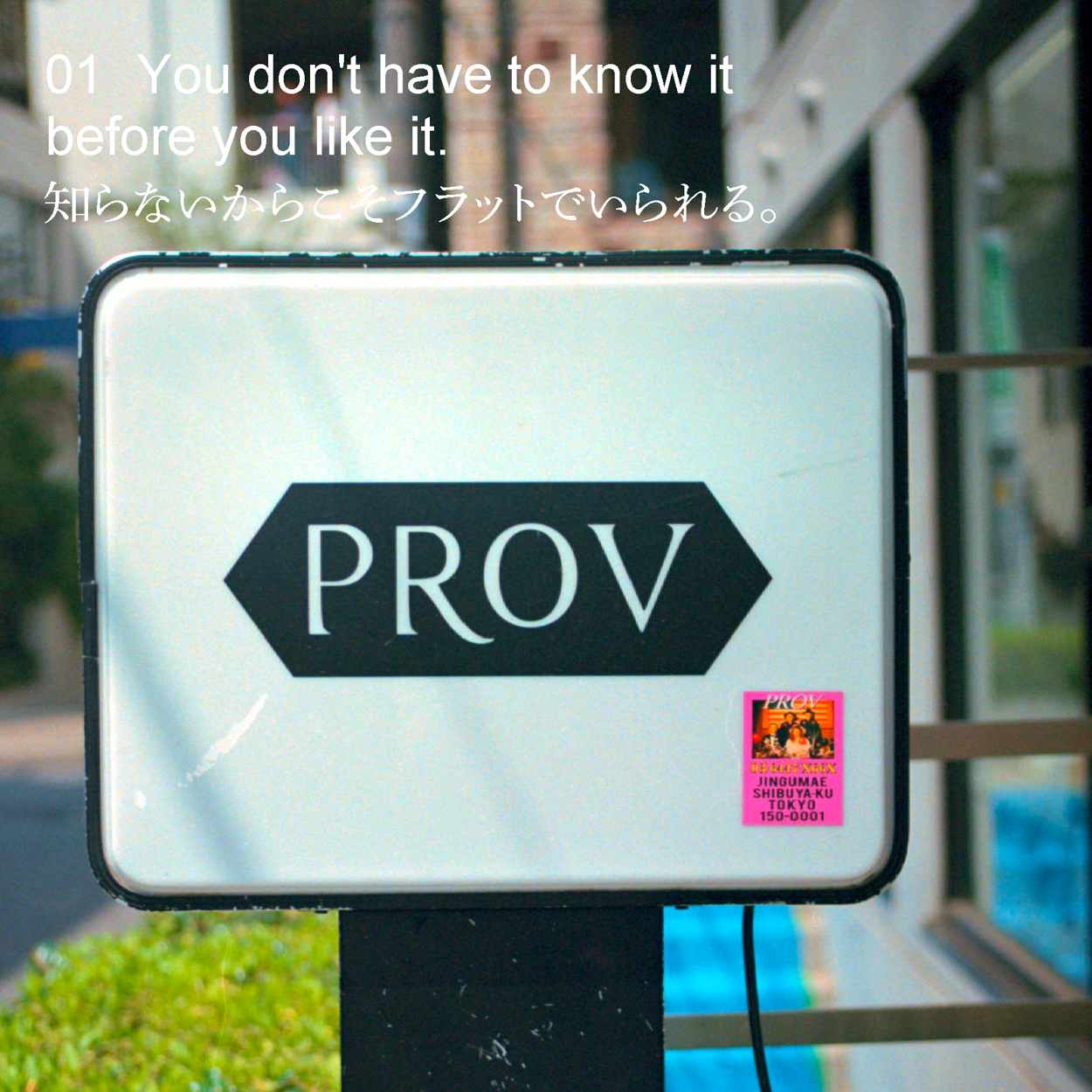
2015年にオープン。原宿からローカルを発信するスケートショップ。店名の由来は“証明”を意味する“PROVE”から。スケートギアや洋服を販売するのみのショップではなく、ローカルキッズの溜まり場としての役割をも担っており、スタッフは全員、シーンに精通したスケーターたち。ポップアップやアートイベントも精力的におこなっている。
ーお店の成り立ちから聞かせていただけますか?
用松:PROV の前にいたセレクトショップでアメリカのスケートブランドを日本に買い付けるバイイングの仕事をしていたんですが、買い付けでたびたび訪れる海外のスケートショップって、自分が見てきた日本のスケートショップとはまた少し雰囲気が違って感じたんですよね。置いている商品はもちろん、立地や環境も。中心地から離れたところにポツンとお店があって、軒先のベンチにはローカルが溜まっていて、店内には商品があるけどあんまり商売っ気はなくて。そこに魅力を感じたというか。
ー確かにアメリカのスケートショップって、そんなイメージがあります。
用松:立地に関しては近所でスケートができることを重視していたり、ゼロから繋がりのないローカルで自分たちのブランドを広げていきたいからとか、いろんな理由があるみたいですけどね。僕自身、ずっとスケートをしてきたし、そういうノリのお店を東京でやってみたいと昔から思っていて。それがオープンのきっかけです。
ーPROVはオープンしてすぐの頃から現地感の強いブランドを数多く置いていた印象です。
用松:日本でまだ見たことないものを置くことは意識していましたね。今でこそある程度の規模感になっているブランドがまだ出たての頃──デッキとTシャツしか作ってないようなスモールブランドだったときからメールでコンタクトを取って、待ち合わせ場所に行ったらデカいダンボールを持ってるスケーター風の男が立ってて(笑)、その男からその場で直接買う、みたいなこともありましたね。それを日本で販売して、広げて、また現地で買い付ける、みたいなことを繰り返しているうちに徐々に横のつながりも増えていって、今ではPROVがディストリビューションさせてもらってる海外のスケートブランドもいくつかあります。


ーDimeやYARDSALE、Polerなど、海外でも勢いがあるスケートブランドが並ぶ中に、アウトドアにルーツがあるGramicciが置いてあるのはすこし不思議な感じがするというか。
用松:そうですよね。PROVだといわゆるアウトドアブランドってやっぱり異質な存在にはなるんですけど、こういうアウトドアのニュアンスがあって、歴史もカルチャーもあるブランドをスケートブランドとミックスするのも面白くない? という提案ですね。
ーセレクトしていただいているのはどのあたりなんですか?
用松:定番の『GRAMICCI PANT』は複数色で抑えつつ、膝でセパレートできる、ちょっとテックっぽいパンツも置いていますね。それと、秋冬はギミックの効いたアウターなんかもいくつか。リブランディングをしてから、少し雰囲気が変わりましたよね。おこがましいですけど、スケートやストリートファッションに傾倒してきた僕自身も直感で「良いな」と思えるものが増えたというか。
GRAMICCI PANT
1980年代、クライマーが欲しい機能をすべて搭載した革新的なパンツとして誕生して以来、長年にわたって愛され続けるGramicciの定番アイテム。ハリコシがあり、激しい動きにも耐える高い耐久性を持つコットンツイルと180度の開脚を可能としたガセットクロッチ、片手で調整できるウェビングベルト&イージーウェストを採用したスケートにも最適な1着。
ー2022年春夏にステファン・ウェンドラーがブランドディレクターに就任してからは、ブランドのルーツであるサブカルチャーに立ち返るようなアイテムも増えまして。
用松:スタッフの肌感ですが、スケーターのお客さんたちに受け入れてもらえている感触があったみたいです。僕個人としては、古着やアウトドアのブームも経由していて、Gramicciに関しては「こういう着方が正解なんです」みたいなステレオタイプを植え付けられている世代だと思っていて。でも、若い子たちからしたらそんなことはまったく関係なくて、一周回ったブランドなんだなって思います。ベルトが付いていて、タフで、シルエットも良い、スケートのときに気楽に穿ける便利なパンツって感じなんでしょうね。


ーイージーパンツとしての側面に反応してもらっているというか。
用松:そうそう。イージーパンツとしてすごく優秀だと思います。このウェビングベルトはいろんなブランドにサンプリングされているディテールだし、そういう背景も込みで信頼できますよね。実際、こないだもPROVで、ニューヨークから来た若いスケーターの子がGramicciのパンツに対して「このパンツはなに?」と反応していたから、こういうルーツがあるGramicciってブランドなんだよ、と説明したら「いいね」と買ってくれたんですよね。ずいぶんフラットに捉えてるんだなって思いました。その子はまだ20代前半くらいで、バリバリ滑ってる子なんですけど。
ーモノの良さに対して、自分の尺度で反応してくれるのは嬉しいですね。
用松:PROVに来る10代後半〜20代くらいの子だとGramicciを知らない子と知ってる子が、ちょうど半々くらいで混ざっている感じがします。売る側の僕らは、Gramicciにルーツがあることをきちんと理解しているし、良いブランドであることは知っているので、お客さんにも安心してレコメンドできるんですよね。

ー話を戻すのですが、置いてあるアイテムなど、お店作りに関する話も聞かせていただきたいです。
用松:誰がバイヤーとかは決めてないんですよね。基本的にはクルー全員で店作りをしています。置いてあるものに関しては、誰かが「これかっこいいですよ」と提案を持ってきたらみんなで見てみて、お店のテイストに合うか、今このタイミングでこれをPROVに置くのはどんな意味があるのか、話し合ってから取り扱うかどうかを決めるようなイメージですね。
ーそういった話し合いのときに決まって出てくるキーワードのようなものってあるんですか?
用松:僕らは“ノリがいい”と表現しているんですけど、ちょっと感覚的なところがあって、言語化が難しいですね。置かせてもらっているブランドについては僕らもしっかりと正しく紹介する責任があるし、売っていく義務があると思っているので、軽く聞こえるかもしれませんけど、簡単な言葉ではないです。

ー全員がスケーターだし、そのあたりの提案もリアルですよね。スケートクルーとしての活動についても聞かせてください。
用松:クルーにビデオグラファーの子がいて、実はもう3年ぐらいスケートビデオを撮り溜めているんですよね。早く出したいんですけど、僕らも手探りでやっているから時間がかかっちゃって(笑)。ようやく面白いかな、と思える水準まではもってこれたので、今夏くらいを目標にリリースしたいですね。
ービデオを撮ってて、さらにビデオグラファーもいるって、この規模感のお店だと少し珍しいことですよね?
用松:そうかもしれないですね。個人的にはスケートカルチャーって“還元”が大事だと思っていて。上下とかではなく横の、ですね。何かやりたいってローカルの子がいたら、お金を出して「やらせてあげるよ」ではなく「環境はあるから一緒にやろうよ」と巻き込んでいきたいというか。スケートに限らず、どの業界も大事なことだと思いますけどね。
ーちなみに、ローカルという言葉が度々出ていますが、“地元”というよりは、もっと概念に近いものなのかなって思ったのですが。
用松:東京におけるローカルって、もっと裾野を広げて考えてもいいのかもな、と考えていて。そもそもお店があるのは原宿なので、ローカルなんてあってないようなものですし(笑)。お店に立ってる子も遊びに来る子も、地方から出てきた子もいれば東京が地元の子もいたりして、みんながミックスして仲良くしているのを見ると、リアルな場所として存在している意味みたいなものを感じるんですよね。PROVをやっていて良かったなと思う瞬間ですね。
ースタッフ同士もみんな仲が良さそうで、東京の、しかも原宿の一等地でこんなにレイドバックしてる雰囲気の店もまた珍しいですよね。
用松:僕ら自身にまだ余裕があって、楽しめている状況なのが大きな理由かもしれませんね。ずっと忙しいお店だったりすると、ただ店頭に立って「サイズあるので言ってください」みたいな、“こなす”接客になっちゃうのも理解できます。それはそれでしょうがないと思うんですけど、うちは裏通りの2階だし、まだてんてこ舞いにはなってないので(笑)。たまにめちゃくちゃ混むこともありますけど、そんなときでも店の端っこでローカルの子が寝てたりして(笑)。びっくりされることもありますけど、そういう光景を見せていくのも悪いことではないよなって気持ちも正直あって。お店に来てくれる若い子たちが買っていく海外のスケートブランドの根幹には、こういうカルチャーが存在しているわけですから。
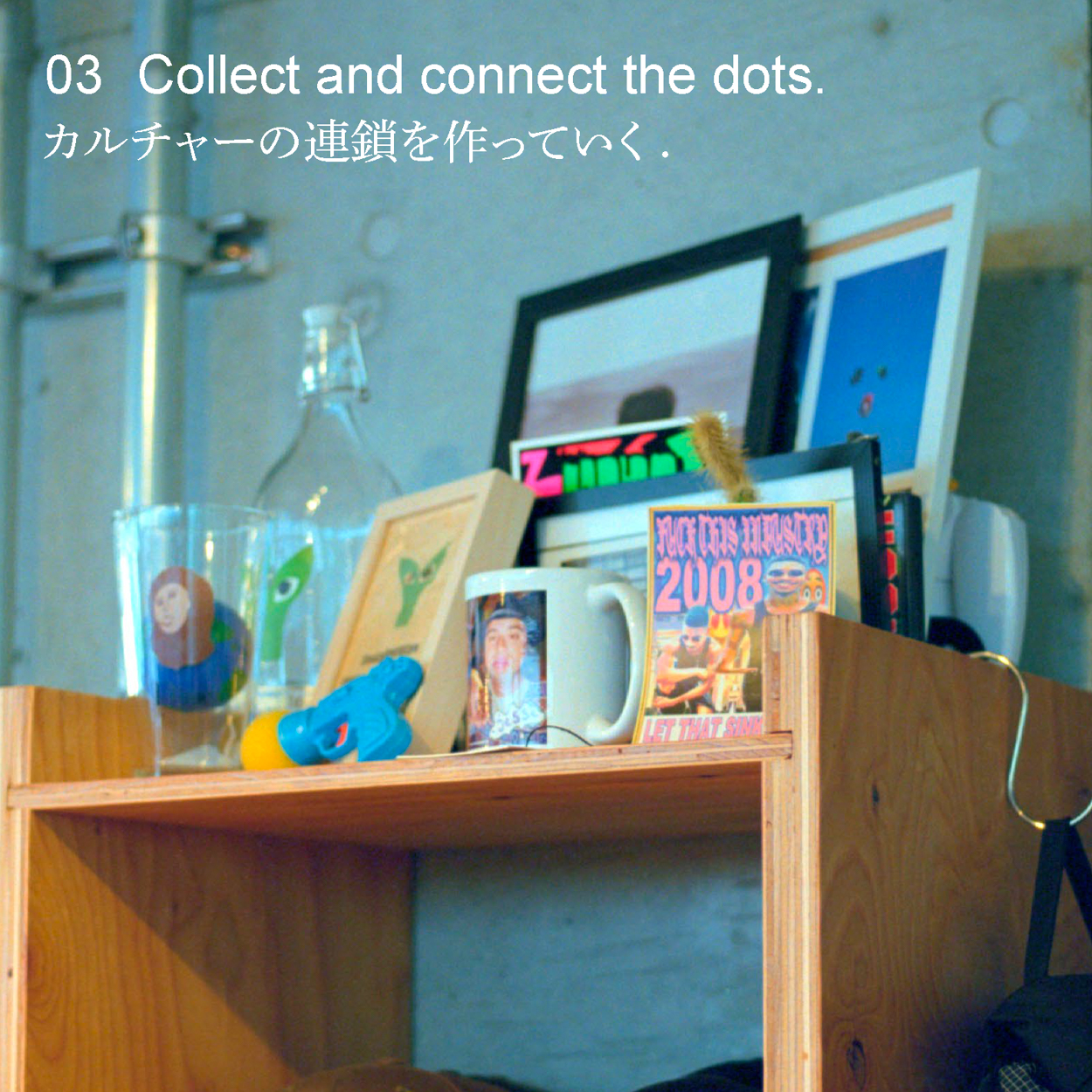
ーアートだったり、PROVの周辺にあるカルチャーについてもう少し掘り下げたいんですが、お店に飾られているアートは、どういうものなんですか。
用松:このレジ後ろのデカいのはアティカス・トーレ(Atticus Torre)っていうアーティストの作品で、PROVでもアティカスがやってるSETTINGSというブランドを取り扱ってるんですけど、彼がうちの元スタッフと友達なんですよね。日本で個展をやった際に展示していた作品の一部をその元スタッフがもらって、お店に置いてくれました。だからいつ持って帰りたいって言われてもおかしくないんですけど(笑)、とりあえず、置いてありますね。


ー店を見渡すと他にもアートがいろいろありますね。
用松:意識して集めてるわけではなく、友達が置いていったものが集まってこうなっちゃっただけというか(笑)。お店とゆかりのあるアーティストが来たときに置いていったものや、贈ってくれたものがほとんどですね。
ーちなみに店内にはアートブックやZINEも置いてありますが、セレクトは用松さんが?
用松:だいたいそうですね。海外で面白そうな写真集が発売されたら取り寄せることもありますし、取り寄せだけでなく、お店の子たちやその友達が作ったZINEだったり、いろいろです。あとはローカルの子たちが作ったZINEだったりとか。

ーそういうものも置いているんですね。
用松:仲良くなって「仲間内でZINEを作ったから置かせてほしいんですけど」と言われて「良いよ良いよ、置いてきな」みたいな。
ーすごく素敵な取り組みですね。これも“還元”だよなって思いました。
用松:そうですね。今っていろんなものが可視化できる時代で、クリエイティブなことを始める子がすごい増えているし、きっとこれからも増え続けていくと思うんです。そんななかで、彼らのアウトプットを見れる場所とか、見せられる機会を作ることって、次の世代に繋げていくという意味ですごく大事だよなと思っています。

ー本当にその通りですね。
用松:特にアートやスケートにおいてはそれが重要だと思っています。自分たちが見ていたシーンのように、次の世代にもそういったものを感じてもらうことがどれほど大切なのかを、みんなで考えていけたら良いですよね。


