

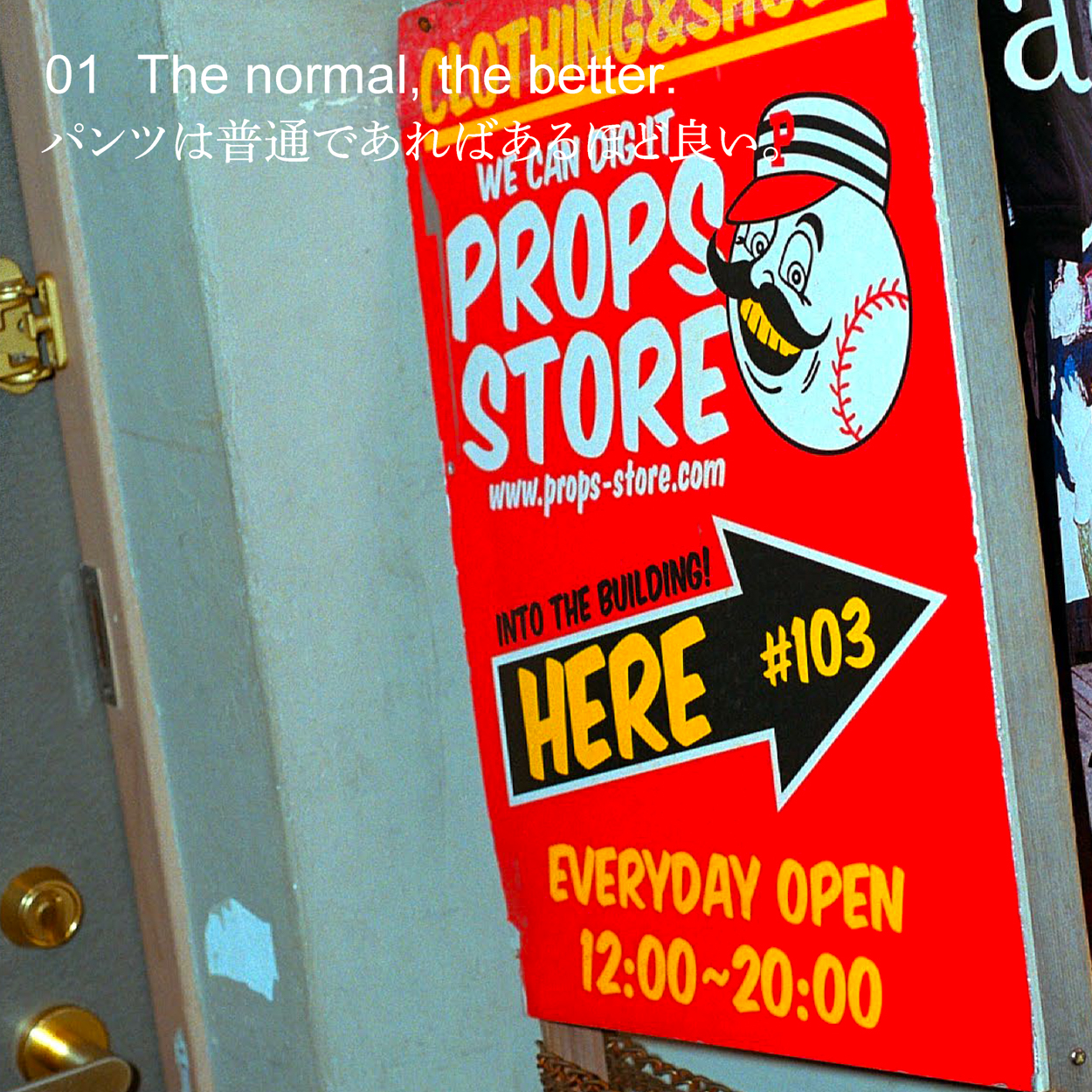
2006年、原宿・キラー通りにオープン。スタッフ自らアメリカ東海岸、西海岸に買い付けに行き、厳選されたアイテムが立ち並ぶインポートショップ。2017年には“別館”として、ユーズドショップ・PROPS STORE ANNEXをオープン。同郷で幼馴染の土井健さんと藤井潤さんが共同オーナーを務める。
ーまずは店名の由来から聞かせていただけますか?
土井:“PROPS”ってそのまま訳すと「小道具」なんですけど、「評価」「尊敬」といった意味のスラングでもあって。僕らは自分たちで買い付けをしていて、お店に置くのは、僕たちが評価できるモノだけ、と決めているんです。それを店頭に並べて、お客様に「いいね」と評価してもらって、買っていただく。そうして世に出たものが評価を得てやがて自分たちに返ってくる。そんなサイクルになったらいいよね、と名付けました。
ー自分たちがそのプロダクトを評価できることが、買い付けの基準であると。
藤井:ただ、凝り固まらず、その時々の気分みたいなものには素直に従うようにしています。店内にはアイテムごとで見るとスタンダードなものが多いですが、やっぱりスタンダードなだけだとどうしたって飽きてしまうし、面白味に欠けてしまうとは思っていて。
土井:DickiesにVANSのようなステレオタイプも僕らは好きですけど、この『Authentic』をローファーに差し替えてみたら面白くない? みたいなことを常に考えていたいんですよね。何を着るかより、どう合わせるかが一番大事というか。“混ぜる”とか“編集する”感覚は、店作りにおいても強く意識していることですね。
ークロスさせたり、ミックスさせたり。
土井:年代を散らしてみたり、一点だけヨーロッパのエッセンスを感じさせるアイテムを混ぜてみたり。セオリーをあえて無視して、サイズ感や色使いも定石から外してミックスしていくと、よく言えば僕らっぽい、PROPS STOREっぽいスタイルになるのかなって思っています。


ーPROPS STOREではGramicciも取り扱っていただいていますが、けっこう厳選してセレクトされていますよね。
藤井:パンツが多めですが、トップスも少し置かせてもらってますね。どちらにしても、うちにあるものと合わせるのが前提なので、型もシンプルなものだけだし、ブラック、ネイビー、カーキ、ベージュ、グレーと、色もすごく偏っちゃってますね。
土井:ある程度決め打ちで選択肢を絞ってあげることが、僕らのような小さいお店の役割かなって。それに僕らは極端なものが好きじゃないから、なるべく普通なものが良いんです。ことパンツに関しては、5年後でも10年後でも穿ける、ということを買い付けのひとつの基準としています。最大公約数をとれるアイテムが基本で、たとえば、デニムだったらLevi’s®︎、ワークパンツだったらDickies、カーゴパンツだったらPROPPER、みたいに。Gramicciのパンツもそういう種類のアイテムだと思っています。
ーPROPS STOREとしてはGramicciをどのように提案しているんですか?
藤井:やっぱりコテコテな合わせではなく、あくまで街着としての提案にはなりますね。
土井:申し訳ないけどアウトドアやクライミングがルーツであることはほぼ無視しちゃっています(笑)。もちろん僕も藤井も、Gramicciがこの手のパンツのオリジネーターであることは理解しているし、リスペクトもありますよ。けれどそのうえで、PROPS STOREとしてはチノパンの延長みたいな感覚で、デイリーなパンツとして扱っています。
藤井:合わせとしてもワークパンツとカーゴパンツの合いの子のようなイメージで、セーターや革靴と掛け合わせるスタイリングを推していますね。
ーお2人にとって、またはPROPS STOREにとってGramicciのベネフィットってどういうところにあると思いますか?
土井:買い付けをする立場として現実的な話をすると、基本的にはいつでも同じものを仕入れることができるのはやっぱりデカいです。持続性が高いプロダクトって、男の子はみんな好きじゃないですか(笑)。みんな自分の制服のようなものを探していると思うんですよね。だから、これから先も在り続けると思わせてくれる普遍性は魅力のひとつなんじゃないかな。これほどプレーンで、なおかつ作りがしっかりしているパンツって、探すとあんまりないですし。
藤井:何も考えずに穿けるパンツって意外と少ないんですよね。でもGramicciはまさしくそう。とにかく気が利いているなって印象です。個人的にはざっくりとしたサイズ展開も嬉しいですね。
土井:S〜Lみたいな、ウエストやレングスを気にしなくてもいいざっくりとしたサイジングも僕らからすると気が利いてるな、と感じるポイントですね。ウエストもレングスも2インチ刻みでサイズの組み合わせが無数にあるって、もうそれだけで選ぶ気がなくなるから(笑)。街で穿くパンツにバチバチな機能性は求めていないですけど、それでもガゼットクロッチやウェビングベルトは普段着としても便利ですしね。
ーちなみに今日は私物も何着か持ってきていただいていますが、土井さんは柄物が多めですね。
土井:ショーツは例外で(笑)。結構かっ飛ばした色柄物も好きなので、お店でも積極的に仕入れるようにしていますね。

奥の3つが土井さんの私物で、手前のものが藤井さんの私物。
ーこれらはどれくらい前のものですか?
土井:90年代に新品で買ったやつですね。今でも古着屋でこの年代のGramicciを掘ったりもするんですけど、「こんなのも作ってたんだ?!」って変な柄とか素材のものがいまだに出てきて、超面白いんですよね。このあたりのシアサッカーやリネンのショーツって、最近復刻してましたよね?
ー2024年春夏シーズンのキーアイテムとして90年代アーカイブのショーツをベースに、アップデートした『JAM SHORT』を出しています。
土井:そういう取り組みはリアル世代から見ても素晴らしいなって思います。僕の私物で良かったら貸すので、資料として使ってください(笑)。

「夏はずっとこのあたりのショーツを穿いています。シアサッカーとか柄物とか、ちょっと変わったやつが好きでたくさん集めていますけど、こっち系は店に出してもあんまり売れないんですよね(土井さん)」

「僕の体型だと『G-SHORTS』は少し丈が長いので、レディースサイズを穿いています。メンズのものより短めに作られているので、好みの丈の長さになるんです(藤井さん)」
O.G. YARN DYE DOBBY PLAID JAM SHORT
多種多様なカルチャーが混ざり合う1980年代の空気感を現代に改めて提案する『O.G.』シリーズより、ブランドが生誕した当時『G-SHORT』と並んで展開されていた『JAM SHORT』がリバイバル。Gramicciのショーツのなかでも特にビッグシルエットで、その名に恥じない、ノリのいい、ジャムれる1着となっている。

ー店内を見渡してみると、統一感がありつつも、良い意味で雑多な感じがあってまさに“編集”だなと感じていました。基本的に、買い付けはアメリカですよね?
藤井:アメリカ東海岸での買い付けが主ですが、西海岸もたまに行きます。LAに滞在していると、ルームシューズのような、地元っぽいアイテムが妙に気になったりするんですよね。そういう、その土地の匂いがするようなものというか、ローカルの空気感を纏ったようなものを持って帰ってこれるのが、現地での買い付けの醍醐味ですね。
土井:現地にいるとその土地のムードに流されて「やっぱりルームシューズにDickiesの合わせは最高だよね」って思いながら買い付けをするんだけど、いざ日本に帰ってきて合わせてみると「いや、これだとコスプレじゃん」と我にかえって、だったらルームシューズをローファーに見立ててスラックスと合わせてみたり、まったく別のカルチャーとしてミリタリーのカーゴパンツを合わせてみたり。そうやって置き換えて取り入れたほうが僕たちらしいというか。
ー場所が変わると、視点が変わる。
土井:そうですね。現地でテンション上がって買って、日本に帰ってからは冷静に自分たちのスタイルに落とし込む、みたいな作業はすごく大切だと思っています。
藤井:そういう意味では、自分たちの中に落とし込めていないアイテムは店内にひとつもないですね。「似合わなそうだから自分が着ることはないけど、モノとしては面白いよね」みたいなアイテムはありますが(笑)。
土井:「着方を提案できないもの、魅力を説明できないものは店に置かない」というのは絶対的なルールですね。

ーそうして集められたモノたちだからか、“THE イーストコースト”でも“THE ウエストコースト”でもない、独特のミックス感があるんですね。
土井:オープンしてすぐの頃なんかは媒体でも「90’s イーストコーストのお店」みたいに紹介されていましたよ。僕らからすると「そういう風に括って欲しくないんだけどな」と思って、途中からはもうそういう括り方とか文言をNGワードにしてもらったりしたんですけど、振り返るとあの頃はもっとローカル感全開というか「これ、今ニューヨークでイケてます!」みたいな見え方になってしまっていたのかもしれません。
ーオーナーの趣味嗜好が反映されているのが個人店の面白さだとは思いますが、今のPROPS STOREには“偏り”のようなものはないように思います。
土井:僕らは特定のブランドのフォロワーではないし、先ほど言ったとおり、極端なものは好みませんから。結局のところ、店内にスタンダードなものが集まるのもそういう理由です。それぞれブランドの背景とか辿っていくとエモい話に出くわしたりもするんですけど、そういうものにとらわれすぎず、もっとフラットに見せることが自分たちのスタイルだよねってことに、長く続けていくなかで気が付きましたね。

ーGramicciのブランドの背景でいうと、2022年春夏シーズンから、クリエイティブディレクターに元STUSSY、Carhartt WIPのステファン・ウェンドラーが就任しています。
藤井:ステファンは展示会のときに見かけましたけど、BSFのキャップ(realmad HECTICで販売していたBlue、Stash、FuturaのUSブランド)を被っていて、ニューヨーク発・裏原経由の日本が好きなんだなぁって思いました(笑)。僕らも世代的にはそんなに離れていないので、彼が通ってきたであろうカルチャーと、それに紐づくモノづくりには共感できる部分が多そうですね。
ーPROPS STOREが大事にしているカルチャーってどういうものでしょう?
土井:断定はできないから感覚的な話になっちゃうんですけど、たとえば、サンフランシスコのグラフィティライターって大抵自転車に乗っているらしいんですよ。なんとなく、B-BOYみたいなコテコテの服装して車移動、とかを想像するじゃないですか。でもそうじゃなくて、土地柄、細い道が多いから小回りが効く自転車で行動しているんですって。僕らはそういう局所的な話とかマナーを知るのがすごく好きなんですよね。
ー興味深い話ですね。
土井:スタイルの話でいうと「絶対に汚さないぞ」って意思表示として、あえてホワイトのフォースワンを履くライターもいるし、汚したくないから靴を脱いでスプレーを吹くライターもいる。こういうのがカルチャーでしょって思っています。ただ、この手の話って別に知っている必要は全然なくて、僕らは好きだから知っているだけであって。

足元にはグラフィティライター・NOE246によるタグが。土井さん曰く「お店に来たマイアミ出身の陽気なライターが『NOEくんに憧れてるんだよ。近くに描いていい?』って言うから描かせたタグがすぐそばにあるんですけど、それは写さなくていいです(笑)」。
ー国や人種、ひいては小規模なコミュニティごとにある「普通」が「カルチャー」なのかもしれませんね。
土井:どこの目線から物事を見るかって話ですよね。モノも同じで、たとえばお店に置いているLOWE’Sのバケツなんかは、アメリカでは超一般的なものだけど、日本ではちょっと珍しいし、雑貨を入れるコンテナみたいにも使えて便利だから置いているんですけど、アメリカ人がお店に来たら、これを見てめっちゃ笑うんですよ。「なんでこんな普通なものがここにあるんだよ!」って。確かに僕らも、アメリカのローカルな洋服屋に亀の子たわしが置いてあるのを見たら「なんでだよ!」って笑い転げると思うんですよ。
ーそれぞれにとっては「普通」な物や事ですもんね。
土井:そうそう。そういうことを知っているか知らないかで優劣はないけど、知っていたほうが絶対に楽しいですよね。海外発祥のカルチャーなんかは特に、1から10までは絶対に分からないんだし、自分が興味あるところだけつまんで、都合良く解釈したらいいんじゃないのって思います。

ーちなみに、アメリカで買い付けたものを買いにアメリカから東京にお客さんが来るのって、ちょっと不思議な気分になりますね。
土井:結構来ますよ。お店のInstagramのアカウントにアメリカ人からDMが来たこともありました。「PROPPERのカーゴパンツが欲しいんだけど、海外に送ってもらえたりする?」みたいな。いやいや、そっち(アメリカ)にめちゃくちゃ売ってんじゃんって(笑)。ただ、彼らの身近なものたちの魅力を、遠く離れた国の僕らが的確に打ち出せているんだなって、嬉しくなりました。 その彼には「Support your local!(地元に金落とせよ!)」って返しましたけどね。


