

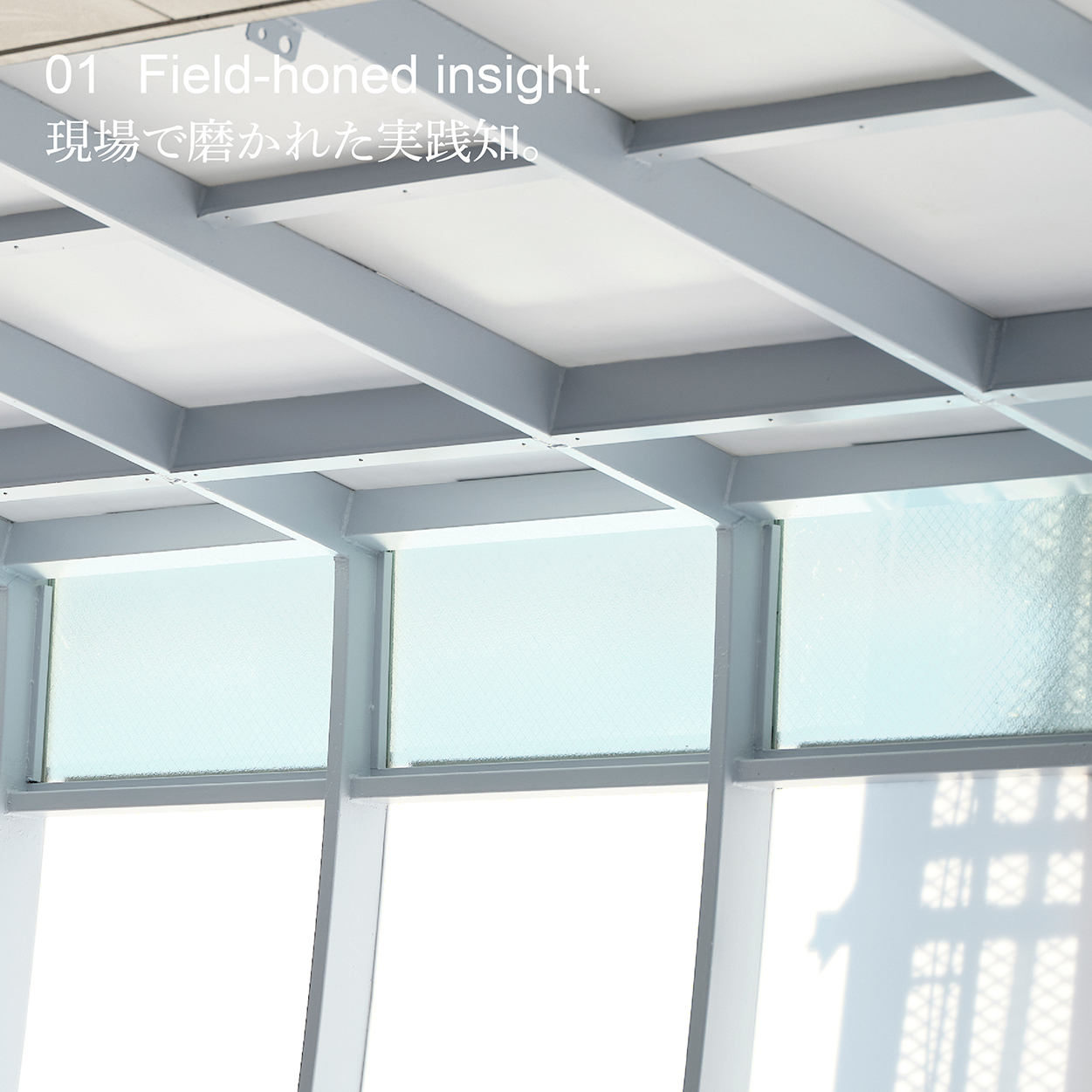
原田学
1972年京都府生まれ。スタイリスト歴は25年以上。タレントやブランドのスタイリングを手がけるほか、2012年より『THE SUKIMONO BOOK』シリーズの執筆、編集を手がける。近頃イチオシのアイテムはタンクトップ。
ー 古着マニアの原田さんはGramicciのことをどう捉えているのか、というところが今回お声がけしたきっかけだったのですが。
原田:今年はさまざまな古着屋さんで「Gramicciのアーカイブが売れている」と耳にしましたね。それも、すごく頻繁に。
ー 実は僕らも小耳には挟んでいましたが、温度感は掴めておらずで。
原田:たくさんの若い子たちがGramicciの、しかも旧ロゴのパンツを欲しがってると聞いていて、「へえ、キテるんだ」という感じです。アウトドアっぽくない古着屋さんもRalph Laurenなどと並べてアーカイブを取り扱い始めていて、実際に街でも若い子が穿いているのをよく見かけました。おそらくこの夏、街で一番流行ったんじゃないかな。
ー ありがたいことです。
原田:同じくアウトドア文脈にあるPatagoniaやL.L.Beanなんかの古着はもう一通り出尽くしたかな、という印象ですが、Gramicciはネクストというか、今まさに渦中にありますよね。まだ掘られてないアーカイブとかもありそうだし。しかしながら、僕自身、定番のモデル以外はどの型にどのような特徴があるのか、あまり分っていないところがあって(笑)。

ー 今日穿いていただいたのが、90年代のアーカイブを復刻した『GADGET PANT』というモデルです。
原田:ポケットの仕様が面白くて選びました。フロントポケットが後ろまで繋がっていて、ハンティングジャケットのようなギア感がありますよね。現行にも古着にも無い独特な雰囲気を感じます。もう何年も前ですが、古着屋で元ネタを見たことがありますよ。それはもうちょっとポケットが浅かったような記憶がありますが。
GADGET PANT
ー Gramicciは1982年に誕生しているので、90年代初頭頃までのブランド初期のモデルがようやく“古着”になってきたのかなと。
原田:そうかもしれませんね。こういうベルト付きのパンツはGramicciが元祖だろうと思いますし、カジュアルウェアの歴史を辿る上でもわりと重要なポジションじゃないかな。
ー といいますと。
原田:たとえば、ちゃんと調べたわけではないから憶測の部分もありますが、ウエストに使われているプラスチックパーツは1980年代初期にはバックパックなどに使用されていました。このパーツをいち早くパンツに取り入れたのはおそらくGramicciで、それが画期的だったんでしょうね。サンプリング(真似)したパンツも多く作られたことで、今もファッションアイテムとして受け入れられているんだろうなと。思えば、僕が高校生の時に穿いていたストリートブランドのショーツだってほぼGramicciみたいな仕様だったし(笑)。
ー ああ、なるほど。Gramicci以前は、この手のパーツは金具を使っていたイメージがあります。
原田:そうなんですよ。こういったプラスチックパーツの信頼性が担保されて、量産され始めた年代でいうと……みたいな。まあこれは答えが分かっていることですから、カンニングみたいなものですけど(笑)。でも、そういうこれまでに得た知識が派生して符合する瞬間に「これだから古着って面白いんだよな」と思ったりします。Gramicciの歴史は、一度ちゃんと調べてみたいですね。

ー 原田さんの脳内には、膨大な量の古着のデータベースがあるってことですね。
原田:自分で掘ってそれによって得た知識はまず忘れないですね。逆に、自分で掘ってなくて、雑誌やWebで見ただけの情報は全然覚えられない(笑)。自分の知識になった感じがしないんですよね。
ー 原田さんといえば『THE SUKIMONO BOOK』をはじめ、各種古着関連の本の監修など、その徹底した探求の姿勢について伺っていけたらと思っているのですが、まずは原田少年と古着、ひいては洋服との出合いから聞いていくのが良さそうかなと。
原田:ファッションは幼い頃……小学校高学年ぐらいからかな。それくらいから好きでした。それがなぜなのかはいまだに分かっていないんですが(笑)。
ー 世の中的には、ファッションやスニーカーのブーム時期と重なりますよね。
原田:大人たちはブームを感じていたかもしれないですね。ただ、自分の両親や周囲の大人たちが熱狂していたかというとそうではなくて。それなのに僕だけなぜか洋服やスニーカーが好きで、学校でも少し浮いた存在でした。「ここのブランドのブラックジーンズが欲しいんだ!」とか親にねだって、決め打ちで買ってもらってましたし。
ー 普通の子どもは親が買ってきたものを無心で着ていますもんね。
原田:そうですよね。それに幼い頃からファッションが好きな人ってだいたい親が洋服好きだし、幼い頃から良いものを着させてもらっているイメージがあります。小学生の頃から『501®︎』に『ALLSTAR』を合わせてました、みたいな。あれ、絶対にウソだと思ってますけど(笑)。

ー (笑)。そこからどのようにして古着の道へ?
原田:僕、けっこう遅いんですよ。個人的に古着熱がピークに達したのが20代の半ば、1990年代の後半ですね。10代から周囲の友人や雑誌の情報に流されて『501®︎』とか古着の定番っぽいものも穿いていたけれど、代々木公園のフリマにさえも行ったことなかった。
ー 今の原田さんからは想像できない古着との距離感ですが、何かのめり込むきっかけがあったということですよね。
原田:きっかけと呼べるような運命的なものでは、まったくないんですよ。20代の頃にはすでにスタイリストとして仕事をしていて、タレントさんの専属スタイリストのようなこともやっていました。ただその頃からずっと、「スタイリストとして食べていくために、自分は何に特化するのが一番いいのだろう?」と自問自答していたんです。当時も流行しているブランドやスタイルは本当に多種多様にありましたが、何を突き詰めれば自分のポジションを確立できるのかを考えたときに、「あ、古着かもしれない」と思ったんですよね。これなら誰にも負けない、という根拠のない自信があったんです。
―「古着かもしれない」、それはなぜですか?
原田:古着を知ることが、“ファッションを知ること”につながると考えていたんです。駆け出しの頃は全然食べられなかったので、原宿のUSAモノを扱うインポートショップでアルバイトをしていたんですが、そのときに近くの古着屋で働く先輩や友人がたくさんできて。彼らが本当に熱心で、知識も豊富だったんですよね。僕がこうした考えに至ったのは、彼らのおかげでもあります。その頃からずっと、今もみんなに助けてもらいっぱなしです。

ー そうして古着スタイリストとしての一歩を踏み出したと。
原田:はい。もちろん、参考書とかで身につけられる知識ではないので実践の中で学ぶしかないわけですが、そんなタイミングで知り合いが新たな雑誌を立ち上げたんですよ。それがヴィンテージとかも紹介しているもので。
ー ほお。
原田:それを見て、「これ、俺がやりたい」と思って(笑)。編集部に「古着のページとかやらせてもらえないですか?」と相談して、すぐにやらせてもらえることになりました。それから4〜5年くらいはやらせてもらったかな。リサーチから選定はもちろん、原稿を書いたりとかも。僕も若かったから「流行? 何それ?」ってスタンスだったし、かなりニッチなものも紹介していたので、編集方針とは合わない部分もあり申し訳なかったですが(笑)、僕にとってはいろいろと広がっていくきっかけのような仕事だったので、すごくありがたかったです。
ー ご自身としても重要なお仕事だったんですね。
原田:その当時、2000年代の初頭くらいかな。まだWebもSNSもそこまで発達していなかったし、とにかく雑誌が強かったですから。古着屋もセレクトショップも、企画書を持って会いに行って「こういう企画をやりたいんです」と提案して気に入ってくれたらなんでも貸してくれましたし。知り合いというか、仕事仲間もたくさん増えていきましたね。

ー そういうさまざまな出会いや縁が繋がり、『THE SUKIMONO BOOK』に集結していくと。改めて『THE SUKIMONO BOOK』とはどういうものなのですか?
原田:名前の通りではありますが、テーマごとに僕がセレクトしたヴィンテージアイテムをコメント付きで紹介した“好き者”に向けて作った本です。“好き者”、僕や読者のことですね(笑)。1冊目を2012年にリリースして、それから別冊など含めて13冊ほどリリースしていますね。
ー 13冊ということは、わりと次から次へと。
原田:うーん、僕の感覚としては、そんなにハイペースではないかな。とにかく本が売れない時代になったことと、古着が流行りすぎてしまって昔ほど集まりにくくなったこととのダブルパンチで。
ー それは確かにそうですね。
原田:なので、ここ何年かは古着をベースにものづくりをしているブランドさんからの依頼や、ヴィンテージ関連のイベントに合わせて作ることが多いです。たとえば、POST OʼALLSやKAPITALから依頼があって作ったものもありますし、NIGO®︎さんのヴィンテージコレクション展の図録も作りました。
ー へえ。そういう派生の仕方をするのは面白いです。
原田:みんなうっすら知り合いですけどね(笑)。でも、『THE SUKIMONO BOOK』を理解して、好いてくれていて、「こういうのできる?」と相談してもらえることはすごくありがたいです。
ー いわゆる“古着解説本”ではない、ということですよね。
原田:うん、僕自身、古着解説本を作ってる意識はないんですよ。一応、ヴィンテージの紹介本として始まったけど、あくまでそれが主題ではないんです。雑誌が別冊で作ってる“古着本”とか、ああいうのもよく依頼してもらって作ったりするんですけど、あれは、ヴィンテージを紹介するための本。でも『THE SUKIMONO BOOK』は僕にとって服の見方、楽しみ方を紹介する本なんですよね。

ー その手がかりとしてヴィンテージがある、みたいな。
原田:そうそう。面白くて解説したくなるような洋服の仕様って、ヴィンテージにしか見つからないものではないんです。現行品にも掘り下げたくなるような魅力に溢れた洋服ってたくさんありますから。でも、そういうのを知ろうとしたときに、ヴィンテージへの理解や造詣があると何倍も楽しめますよ、という話を何冊にも渡って訴求したいと思っていて。
ー なるほど。
原田:特定の商品を売ることが目的ではなくて、「こういうのもありなんだ」とか、「こういうのが面白いのか」を知ってもらって、明日からの服選びのヒントにしてもらえたらいいなと思うんですよね。だから、いわゆるヴィンテージ好きには僕の本は全然ウケないんです(笑)。でも、それも納得できています。すごくレアなものを載せているわけではないし、どちらかというと特別なものは積極的に載せないようにしていますから。
ー むしろ、実際に洋服を作っている人やファッションに関連した仕事に従事している人からのウケが良さそうな印象が。
原田:まさしくそうなんですよ。嬉しいことに、アパレルの人やファッション業界の人からは「企画会議のときにみんなで見て、参考にしながら服作りをしてます」と言ってもらっていて。“好き者”には深く刺さっているようなので、狙い通りです(笑)。
ー 現行品でも、洋服を作るときにそういう引き出しはかなり必要になりますもんね。
原田:古着って、同じブランドの同じ型のアイテムでも年代ごとに細かく仕様が変わったりしていて、深く掘れば掘るほど細かな面白さを発見できるんです。そういう“細かいこと”を研究していくと、思わぬ横のつながりや時代背景が見えてきたりして、それがモノづくりをするうえでの世界観の補強や発想のヒントになったりするんでしょうね。

ー 原田さんのような、学者的なスタイリストもまた少し珍しい気がします。
原田:人のスタイリングを組む場合はこの知識が足枷になって、逆に凝り固まっちゃうこともあるんですよね(笑)。このアイテムはウエスタンにルーツがあるから、どこかにウエスタンっぽい要素を足しておこう、みたいな。こういう頭でっかちな組み方でもまとまりは出るけど、よくないやり方かもな、と個人的には思います。
ー なるほど。
原田:逆に、そういう知識を持っていない人が勢いで組んだ方が面白いスタイリングが出来上がることも往々にしてありますから。そういうのを目の当たりにしたときに、「ああ、俺ってしょうもないやつだな」って思う(笑)。
ー 確かに、知らない人がやることの面白さはありますよね。
原田:ぶっ飛べますもんね。セオリーとか全部無視、みたいな。僕にはできないから、ちょっと憧れちゃいますね。
ー それはかなり、原田さんならではの悩みですね(笑)。結果として正当派にまとまってしまうみたいなことはありそうです。
原田:このことはずっと意識しているから、歴史や背景にあえて背いたものを1点だけ入れてみよう、とかも考えるんだけど、いや、そんな打算みたいなものは無い方が良いに決まってんじゃん!って思ってる自分もいたりします。
ー なるほど。面白いですね。では、そろそろ締めようかなと思うのですが、これからスタイリストとしてどういうことをやっていきたいですか?
原田:もっと知識を増やしていきたいですね。まだ評価されていない面白いものをどんどん紹介していきたい。この活動って、自分自身の知的好奇心が満たされるだけでなく、絶対にファッション業界への貢献になっていると思うんです。誰かが紹介しないと忘れ去られてしまうかもしれないものを保護するような作業というか。それに、丁寧にまとめて発信したら、必ず何かが起こるんですよ。特定のアイテムが一時的に流行ったりとか、何年か経ってからオマージュしたであろう現行品が出たりとか。それがファッションの“次”に繋がっているんだとしたら、それ以上嬉しいことはないですね。


